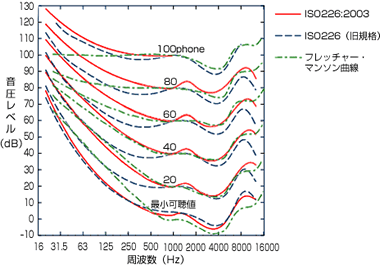等ラウドネス曲線 読み: とうらうどねすきょくせん
- ホーム
- 等ラウドネス曲線
用語解説
ラウドネス(人間の聴覚で感じる音の大きさ)と、音圧レベル(音の物理的な値)を表した曲線。
周波数の異なる純音を人間の耳で聞いた際、それらの音の大きさが等しく聞こえる値(音圧レベル)を結んだ曲線のこと。等ラウドネスレベル曲線、等感曲線などとも呼ばれる。この曲線から、人間の耳には周波数特性があり、音の高さによって聴取感度が異なることが見て取れる。
1930年代にベル研究所(米国)のフレッチャーとマンソンの測定により作られた等ラウドネス曲線は、フレッチャー・マンソン曲線などとも呼ばれる。1950年代に英国のロビンソンとダッドソンによって測定された等ラウドネス曲線(ロビンソン・ダッドソン曲線)はISO226として国際規格化された。この国際規格は2003年に改正され、ISO226:2003となっている。